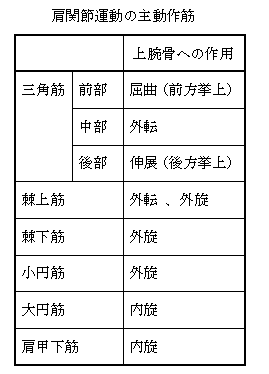2011年11月に<片頭痛の病態生理と鍼灸治療の検討>を記したが、その全面改訂版を記すことにした。タイトルも<血管性頭痛の病態生理と鍼灸治療の検討Ver.2.0>に変更した。
1.三叉神経血管説の整理
片頭痛の病態生理は、なお不明な点は少なくないが、現在では「三叉神経血管説」が最も有力 視されている。これは神経因子(脳の大血管や脳硬膜に分布する三叉神経刺激による痛み) に加え、血管因子(この血管から放出された血管拡張物質CGPR)による複合性の痛みとして 説明される。この説明は難解だが、簡単に内容を示せば次のようになる。
一段目:三叉神経第1枝が中心となる痛みがある。これは神経因子の反応。
二段目:三叉神経血管拡張物質(CGPR)放出することで血管拡張と炎症が生ずるとする血管 因子の反応。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
2.片頭痛に対する薬物療法の変化
私が30年前に病院勤務だった頃は、片頭痛に対して酒石酸エルゴタミン(商品名カフェルゴット)投与が定石だった。トリプタンが販売されて随分事情は好転した。
1)従来的消炎鎮痛剤
いわゆる「痛み止め」。片頭痛の痛みは神経因子+血管因子の複合であるが、この神経因子に対する作用のみになる。血管因子に対しては無処置であるから、鎮痛効果に乏しい。
2)酒石酸エルゴタミン
一世代前の片頭痛の特効薬。30年前頃筆者が病院勤務だった頃は、これが定番だった。主成分はカフェインで、これには血管収縮作用がある。拡張しようとしている血管を、拡張させないという予防効果がある。しかし拡張し、拍動性頭痛となった後は、それを改善させるだけの力はない。
3)トリプタン製剤
現在の主流薬。三叉神経終末からの血管拡張物質(CGPR)放出を止める作用がある。すなわち血管因子の痛みの連鎖を停止させる作用がある。拍動性の痛みも鎮痛できる。
3.筆者の片頭痛の針灸治療の変化
率直にいうなら、緊張性頭痛とは異なり、片頭痛が針灸にくることはマレである。もともと西洋人に比べ、日本人が片頭痛になることは少なく、また発作時は院困難である。片頭痛予防に針灸しようと考えるような周到な者は、医師の薬物療法をうけているからである。
結果的に、数少ない臨床経験から、推論することにならざるを得ない。
1)動脈血管壁刺針
拍動性頭痛期の治療としては、拍動している外頸動脈の分枝を強圧すると数秒間痛みが減少することが知られている。そこで異常拡張を抑える意味で動脈血管壁に対する刺激のが検討されてきた。たとえば浅側頭動脈に対する和髎刺針であるが、大した効果は得られなかった。
その理由は、<三叉神経血管説>によれば、「頭蓋外拍動部が痛むのではなく、痛みは頭蓋内硬膜部の静脈血管やこの血管にまとわりく三叉神経第1枝の興奮の結果として痛む」からであり、そもそも頭蓋外の痛みは病態の本質とは異なるものだからだろう。
2)上部頸椎への刺激
片頭痛の痛みは、神経性因子と血管性因子の複合である。神経性因子に働きかける治療とは、脳動脈に分布する三叉神経の治療をいう。しかし頭蓋内については針灸で直接的にアプローチはできないから、三叉神経-大後頭神経症候群の治療と同じように扱う他ない。
すなわち頸にある上位頸神経(C1~C3)へ刺激を加え、上位頸神経の興奮を取り除くような針が有効だとする見解がある。
ただし痛みの主体である血管性因子について働きかける治療はしていないのだから、治療効果は限定的なものになるであろう。
3)足趾間刺針とグロムス機構刺激
①上衝による頭痛には足指間を刺激する
筆者が針灸臨床の駆け出しの頃、臨床経験不足を補うために、玉川病院症例検討会の報告資料(先輩達の残した症例報告数千例)を読みあさった時期があった。そして上衝タイプ(のぼせて赤ら顔)の強い頭痛には、足指間の最大圧痛部を刺激すると頭痛が改善したとの報告が多いとの報告が多いことが判明した。
②内侠谿刺針
自分なりに患者の足趾間圧痛を多数調べてみると、足指間の最大圧痛点は、第3趾第4趾間に出現することが多いということもわかった。この圧痛は、侠谿の内側にあるので、筆者はこれを内侠谿と命名した(実際の臨床では内侠谿に限定することなく、足趾間の最大圧痛点を取穴する)。
最大圧痛点にに2~3分間置針するだけで痛みが取れてくることを多数確認できた。
この頭痛に対する効果は、強い頭痛であれば効果があり、弱い頭痛ではあまり効果がなかった。
また針灸が効果あるか否かは、治療時の頭痛が拍動性か非拍動性かに関係し、非拍動性のタイプは有効となる場合が多いように思った。
③グロムス機構
足趾間の圧痛点に刺針で頭痛が改善する理由は、グロムス機構の機序が考えられる。グロムス機構とは、動脈脈吻合あるいは動動脈吻合部をいう。一般的に血液循環は動脈→毛細血管→静脈と移行するが、全部の血流が毛細血管まで達するのではなく、一部は小動脈から小静脈へとショートカットする。この血行動態の変化を起こす水門に相当するのがグロムス機構である。
グロムス機構の性質として、例えば1カ所の水門が閉じると、それが全身のグロムスの水門も閉じられるという仕組みがある。つまり足母趾部グロムス水門を閉じると、脳内のグロムスも閉じ、血流減少するという機序が考えられるということである。