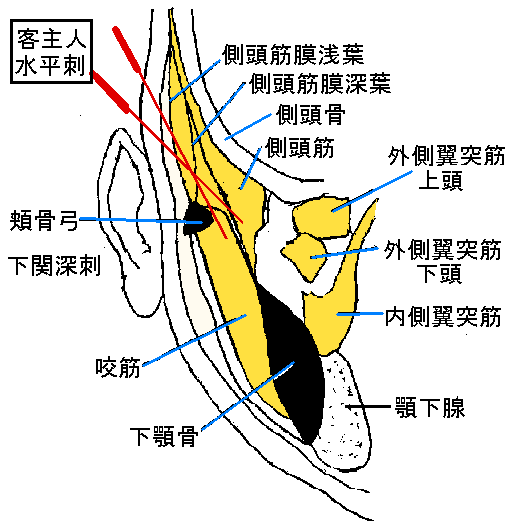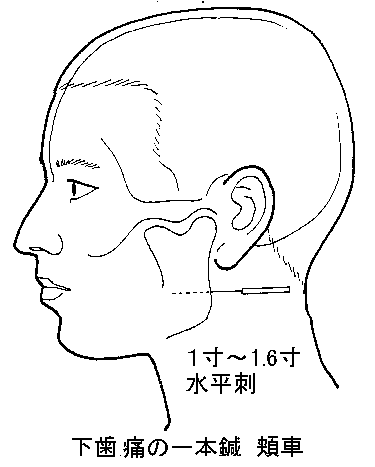1.序
『黄帝内経』が編纂されたのは漢の時代(BC202~AD220)だとされている。当時、道教は儒教とならんで、中国人の精神構造の基盤となった。中国の古代医学も道教の影響を強く受けていたと考えられる。道教を学習することは中国の針灸古典の背景を知る上でも興味深いことである。
私は鍼灸学校卒業してすぐの頃、道教の古典的名著であるアンリ・マスペロ著川勝義雄訳『道教』東洋文庫、平凡社刊 昭和53年(1950年原著出版) を購入して読んでみた。この著作は「道教とは何か」に対する一つの確固たる回答であり、欧米の学会に大きな刺激を与えたという。しかしそれでも35年前の私にとっては難解すぎた。それを今になって読み返してみたが、今回は意外にも興味深く読むことができた。というのも、東洋医学に対してある程度の知識や経験をもったので、本書を自分の考えと対峙しながら、読めたのが原因だろう。道教の興味深かった点を、筆者の解釈を加えて紹介する。
2.著者アンリ・マスペロ Henri MASPERO とは
![]()
フランス人中国学研究者アンリ・マスペロ(1883-1945)は、研究途中で「道教」について、自分がほとんど何も理解していないことを改めて知った。その上で、道教は儒教とならんで中国人の精神構造を知る上での鍵であるという事実に突き当たった。マスペロは当時の道教の歴史と文献を学問的に探ろうとした最初の人であった。マスペロが生前に発表された原稿は少なかったが、死後書斎を整理してみて、道教については膨大な未発表原稿が発見された。
これらの原稿は、マスペロの妻と友人が整理して本書として誕生した。本著は、西洋の者が道教を知る上で最もスタンダードなものとされている。なおマスペロは1944年ドイツに拉致され、その翌年獄中で非業の死をとげた。マスペロは日本語学習の必要性を理解し、我が国にも2年間滞在したことがある。
3.不死への修業
道教では死んでしまえば霊魂も消えてなくなると考えていたので、生き続ける身体の保持の方法が興味の対象となった。その方法は単なる延命ではなく、生きている期間内に不死の身体に取り替えることだった。
身体を不死にする方法は、養形と養神に区分され、それぞれに対して様々な実践的なプログラムが用意されていたが、どれも厳しい修行を必要とした。
養形:物質的な身体の老衰と死の原因の除去。 →食餌法や呼吸術
養神:身体内部にいる種々の超越的存在(悪さをする精霊、霊魂など)ににらみをきかせ、自分勝手に悪さをさせない。 →精神集中や瞑想
4.呼吸法
臍下丹田の「丹」には赤いという意味があり、「田」は生産する場所という意味がある。すなわち丹田は、生き続けている間、生命の炎が燃えている場所と考えていた。この丹田では精を養う場所だった。火が燃え続けるには空気が必要だが、普通の呼吸法では空気は肺にまでしか入らない。丹田の炎を大きく燃やし続けるには腹まで空気を入れるべきであると考えるようになった。その方法とは次の2通りある。
1)胎息(息を飲み込んで消化管に至らしむ)
呼吸器官は胸までしかないが、消化管は食道を通って腹全体に配置されている。息を吸うのでなく、息を飲み込むようにすることで胃腸に空気が入るから、臍下3寸(=関元に相当)にある丹田の炎を大きく燃やすことで精を養う能力を増やすことができる。臍下丹田にある精が、そこに入ってきた空気と結合して神(=正常な意識。この神というのは霊魂とな別物)が生ずる。
腹にまで空気を入れる呼吸法を胎息とよぶ。これは母の胎内における胎児の呼吸の方法だからである。
臍下丹田に入った気は、その後に髄管によって脳に導かれ、脳から再び胸に降りていく。3つの丹田(後述)をこのように回り終えたら、口から吐き出される。あるいは単に気を巡らせるのではなく、気を身体の中で意のままに動きまさせる。病気の時は、疾患のある場所を治すため、そこへ気を導く。
2)閉気(息を閉じ込める)
凡人は、吸った空気はすぐに吐いてしまうから、空気の中に含まれている滋養を充分に吸収できない。気を深部にまで巡らすには、長時間息を止めておく(閉気)ことが必要である。閉息して、気のもつ滋養を吸収できる時間をできるだけ長くする。
5.食餌法
1)三つの丹田の働きを妨げる三虫
身体を、上部(頭と腕)、中部(胸)、下部(腹と脚)に三分割できる。各部には上丹田・中丹田・下丹田とよばれるそれぞれの司令部がある。丹とは紅と同様な意味で、炎に通じている。生命の炎が燃え続けているためには、気(空気)は不可欠である。
上丹田:脳中にあり、泥丸(ニーワン)宮という。これはサンスクリット語のニルバーナ=涅槃に由来している。上丹田は知性をつかさどる。なお涅槃(ねはん)とは煩悩から超越した境地のこと。転じて聖者の死を涅槃というようになった。上丹田に行く気が不足すれば知性を失う。
中丹田:心臓のそばには絳宮(こうきゅう)がある。絳(こう)とは深紅の意味がある。
血液循環の元締めだからであろう。心拍数の増減させること、すなわち感情の起伏に関与している。
下丹田:臍の下3寸の処(関元の部位)にある。下丹田は精を養っている部で、精に気が注入されて初めて神(正常な精神)ができる。精力(精神や肉体の活動する力)をつくる源でもある。
2)辟穀(へきこく)-三虫退治のために
三つの丹田にはそれぞれの守護神がいて、悪い精霊や悪気から丹田を守っている。しかし守護神のそばには有害な三虫あるいは三尸(=屍)がいて丹田を攻撃して老衰や病気の原因をつくる。道士(道教の修業者)は、できるだけ早く三虫を取り除かねばならない。穀物を食べると、必然的にカス(大便の材料)が出て、カスは濁気を醸成する。この濁気が三虫を滋養し、疾病を起こす。三虫を取り除くには、穀物を絶たねばならない。これを辟穀(へきこく)とよぶ。辟穀は道士修業の基本である。穀物の代りに松実・きのこ・薬草などを食して体内の気を清澄に保つ。
2)霊薬としての丹薬
①丹薬の製造
辟穀しただけでは、三虫を絶滅しきれず、丹薬の服用も欠かせすことができない。丹薬は丹砂(=辰砂)ともいい、自然界では硫化水銀として存在している。純粋な丹砂は、朱色だが、普通は不純物を含むので暗褐色である。丹砂を炉400~600 ℃ に加熱して出た蒸気を冷やすことで水銀を取り出す。
水銀蒸気は目にみえず、瞬時に蒸発してなくなる。この段階では見えないものを集めなくてはならないので、2000年前の中国人が水銀精製法を発明したことは驚きである。熱を加える作業をした職人は、おそらく霊薬中毒(=水銀中毒)で発病しただろう。
水銀がなぜ霊薬だと思ったのかは定かではないが、水銀は金属でありながら重い液体であり、さらに常温でも気化(重さがなくなる)して次第に消滅することなどの特性があることなどが考えられる。
古代ヨーロッパの錬金術師が、鉛などの卑金属を金に変える際の触媒となると考えた霊薬は辰砂のことで、辰砂は西洋では「賢者の石」ともよばれる。賢者の石との名称は、童話「ハリー・ポッターと賢者の石」ですっかり有名になった。
![]()
![]()
![]()
②硫黄と水銀の特殊性
なぜ、硫黄と水銀が特別なのかについては、最もな理由があった。
①自然界には辰砂 しんしゃ(=硫化水銀HgS)という朱色の鉱石がある。これを空気中で加熱(600℃)すると、次の化学変化が起こる。発生した水銀蒸気を冷やすことで水銀抽出できる。なお二酸化硫黄は空気中に拡散され残らない。
②この水銀単体を空気中でさらに加熱(350℃)することで朱色の酸化水銀になる。
③さらに加熱(450℃)すると酸化水銀が分解され、水銀単体に戻すことができる。
②③は可逆反応であり、空気中で加熱するときの温度の違いにより繰り返し反応を起こすことができる。 辰砂を焼くだけで、銀色→朱色→銀色→朱色と繰り返し色が変化することが、神秘性を感じたとしても不思議ではない。
![]()
3)丹薬の効能
丹薬は永遠の命や美容などで効果があると信じられていた。丹薬が永遠の命を実現できるものとする考え方は、遺体を辰砂溶液に浸しておくと、いつまでも腐敗しないという実例がヒントになっているのだろう。ちなみに昭和天皇の遺体も布にくるまれた後、辰砂液につけられ、真っ赤だったという証言もある。天皇のような高貴な身分の人は、死去から遺体を埋めるまでに相当な期間を要するので、腐敗を防ぐ手立てが必要になったという。
秦の始皇帝は永遠の命を求め、水銀入りの薬や食べ物を摂取していたことによって逆に命を落とした。他にも多数の権力者が水銀中毒で死亡した。当時から、丹薬服用の危険性は知られていた。しかし至高の価値を得るためには、命を預けた賭けが必要で、また人格によって毒にも薬にもなるという人格が試される試験でもあったという。
なお稲荷神社の鳥居や神社の社殿などの塗料して古来から用いられた朱の原材料も、水銀=丹である。丹は木材の防腐剤として使われてきた。朱色は生命の躍動を現すとともに、古来災厄を防ぐ色としても重視されきた。
臍下3寸の関元穴あたりを臍下丹田とよぶ。この部が充実して温かいことが、命の炎が燃焼しているという意味であった。
※現代での有機水銀中毒事例としては水俣病が知られている。
.錬金術と錬丹術
古代から西洋では錬金術として金の抽出が行われていた。これは金鉱石を砕いて水銀を加えて加熱し、水銀蒸気を蒸発させて純粋な金をつくるものだった。卑金属から貴金属をつくる研究も行われたが、これらは失敗した。しかし近代化学の基礎を築いたという点で評価されている。
錬金術と錬丹術における霊薬の製法には、共通点があるので、錬金術を研究することは練丹術の研究にもつながった。しかし中国では錬金術よりも錬丹術が重要視された。すなわち黄金よりも永遠の生命に価値が置かれた。山奥の洞窟に住み続ける古代中国の仙人は、練丹術を修得しているとされた。仙人はたまに町にでかけることもあるということで、何とか彼らに出会って、その秘法を教えてもらうのも一つの方法とされた。そうした仙人の住む深山の世界は、水墨画において幽玄を感じ取れるものとして描かれている。
![]()
☆中国の柴暁明先生が、上記の私のブログを中国語に訳して下さいました。感謝致します。文面は次の通りです。
現代の中国でも、上流階級の者を中心に、道教の辟穀は流行っているようです。
何万元から何十万元でもかかって一週間の辟穀修業する方も結構多いそうです。
新聞記事を鵜呑みにして、浅い知識で勝手に今週辟穀しようと宣言する庶民たちは少なくないです。
このブログは、中国人にとって必要な基礎内容です。私は翻訳する前は、道教に対する認識も薄かったですが、このブログのお陰で、以前より深く認識できるようになりました。
道教によって影響をうけた古代中国の生命観 Ver.1.3
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0Nzg5MjkzNQ==&mid=2247483824&idx=1&sn=f063f536f5a61784f4d0358d20421572&chksm=fb463a18cc31b30e656ef7b3e859ad4f06fe432d219ec8df057fb5670dcd203c6a215d5c7486&token=394854727&lang=zh_CN#rd
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0Nzg5MjkzNQ==&mid=2247483824&idx=1&sn=f063f536f5a61784f4d0358d20421572&chksm=fb463a18cc31b30e656ef7b3e859ad4f06fe432d219ec8df057fb5670dcd203c6a215d5c7486&token=394854727&lang=zh_CN#rd