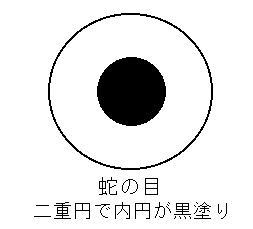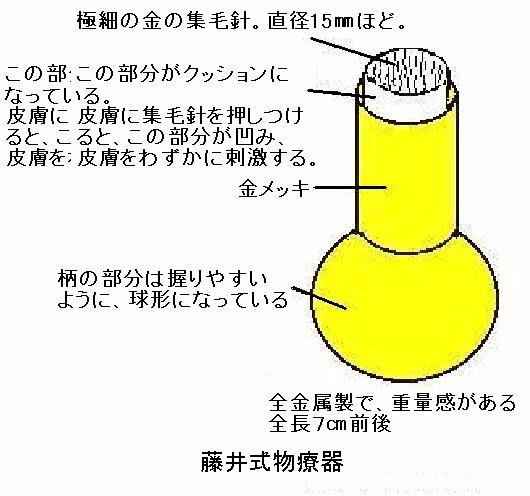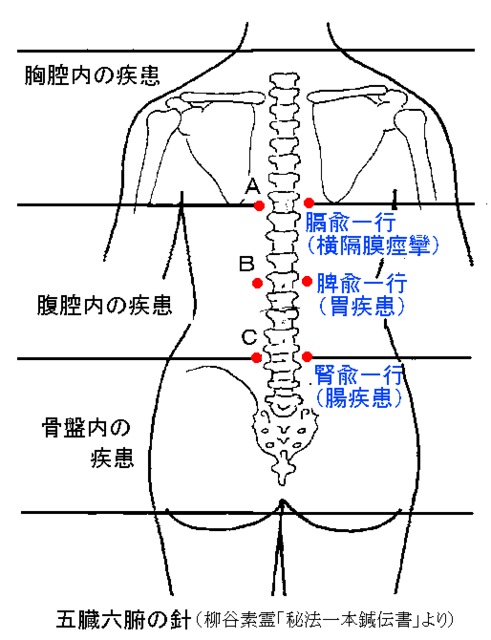1.合谷
1)合谷押圧で、排便しやすくなるか?
十年ほど前、私が主催した勉強会の席上、小宮猛史氏が「排便困難時は、便器に座って左右の合谷を強圧すると排便しやすくなる」(代田文彦編、玉川病院生情報会著「鍼灸臨床生情報②」医道の日本社にも掲載)と、意外な見解を提示した。それを聞いた私は、合谷は大腸経に属するので、そういうことがあるのかとは思ったが、それ以上に話を進展させられなかった。以来この発言内容は、私の中で未解決課題として保留されつづけた。
2)骨盤底筋協調運動障害
排便しようとして腹圧上昇→骨盤底筋はゆるんで下降→肛門直腸角が直角になる→スムーズな排便。これが生理的な排便機序になる。

肛門と直腸は、立位や仰臥位では肛門直腸角が直角に折れまがっているので、この姿勢では糞便が通過しにくい構造になっている。洋式トイレの場合は椅座で排便するので、肛門直腸角は水平に近づくので、排便しやすい体勢になる。さらに上体を前傾してつま先立ち姿勢にすると、肛門直腸角度はより水平に近づくので、もっと排便しやすくなる。
この肛門直腸角を生むのはで恥骨から直腸を紐でひかっけ、たぐり寄せるような構造になっている。この恥骨直腸筋は肛門挙筋の一つである。
※肛門挙筋3種:肛門挙筋:腸骨尾骨筋・恥骨尾骨筋・恥骨直腸筋がある。恥骨尾骨筋はPC筋という名称としても知られ、ペニスが勃起するときにペニス海綿体に血液を送るポンプの役割および海綿体に送られた血液をペニスから体内に戻らないように圧迫する役割がある。PC筋が正常に働かなければ中折れ等の障害を引き起こすとされる。
3)合谷押圧の意義
上体前傾姿勢にして排便しやすくする姿勢は、ちょうど合谷を押圧する時の姿勢に似ていることを発見した。本稿冒頭で「合谷押圧で、排便しやすくなるか?」との疑問への回答は、「合谷押圧する姿勢をとっていきむことで排便をしやすくなる」のではないかとなる。
4)痔疾に対する孔最の治効理由(三島泰之)
スムーズに排便できない場合、いきむ力を増すことになる。和式の排便スタイルはでは、膝を相当窮屈にまげた姿勢で、手は自然と結ばれ、前腕は屈筋に力が入った姿勢となる。前腕屈筋群では、孔最穴あたりから手首に向かって一番力が入った状態になる。痔の痛みの中での排便のポーズは、この延長上である。排便困難→いきみ→痔核の悪化という機序をたどる。(「今日から使える身近な疾患35の治療法」医道の日本社刊 2001年3月1日出版)。
2.澤田流神門

1)澤田流神門は便秘に効果あるのか?
代田文誌著「鍼灸治療基礎学」を読むと、「神門の灸(米粒大5壮)が便秘に効果ある」旨のことが書いてある。ただし神門がなぜ便秘に効くのかは、誰に聞いても納得できる回答は返ってこなかった。
2)神門刺針が遠隔部の圧痛に及ぼす影響
(塩沢芳一「刺針と圧痛との関係の研究 第5報 神門について」日鍼灸誌、11巻1号、昭36.12.1)
塩沢芳一は合谷の圧痛と澤田流神門の関係を調べた。その結果、合谷の圧痛は神門の刺針によって、 拭うがごとく消退するものが多いことが判明した。また澤田流神門に針をしたとき、中府・膻中・上不容・大巨の圧痛が変化するかどうかを229例調べた。この結果、合谷の圧痛が減っていれば、他のツボの圧痛もとれる傾向にあった。なお澤田流神門に針をすると合谷の圧痛が減り、合谷に針をすると澤田流神門の圧痛が変化することは、代田文誌の日常臨床からも周知していることだったという。

以上の報告から、神門刺針は、合谷はもちろん、身体全体の過敏性をゆるめる作用があるのではないかと推定された。その作用の一つが痙攣性便秘ということになる。
塩沢の調査データを見ると神門刺針が全身的なツボ圧痛反応を弱くしていることが分かり、今更ながら非常に驚いている。ただし神門だけがこのような特別な効果があるのか否かは読み取ることができない。
・
3)澤田流神門の皮内針で腹痛がとれ、便通のついた症例(奧定由香子氏報告)
本症例報告は、代田文彦編、玉川病院生情報会著「鍼灸臨床生情報」医道の日本社刊による。
普段から便秘傾向あり。数日前から便秘していたので、起床時に牛乳1杯とコーヒー2杯を飲むと、突然腹部全体に仙痛出現。すぐに排便(普通便)はあったが仙痛不変だった。背部へ施術すると自発痛は治まったが、前屈姿勢・歩行などで腹筋を緊張させる姿勢で腹部がズキーンと痛む。腹痛に効きそうな下肢部穴をいろいろ押圧するも症状は緩解せず。しかし左澤田流神門を押圧しながら前屈姿勢をとらせると痛みはなかった。この穴に皮内針を入れると、前屈姿勢や歩行でも痛みはでなかった。その後毎日便通があったのだが、皮内針をはずすと便秘になってしまた。以上。
この症例で分かることは、澤田流神門=蠕動運動亢進させて便秘を治す、という構図ではなく、澤田流神門=腹部筋緊張を改善というものである。そこから見えてくるのは、腹部筋緊張と便秘の間につながりがりそうだということである。直腸や肛門は副交感神経優位なので内臓体壁反射を起こさないのだが、腹筋緊張が便秘に関係するとすれば、話は別になってくるだろう。神門刺激→前屈姿勢可能→便器で前傾姿勢ができるので肛門直腸角度開く→排便容易との因果関係があるかもしれない。
便秘を、自律神経失調の結果だとする見方は、間違いではないのだが、基本的に鍼灸治療は体性神経に働きかけるものであって、自律神経に直接的に作用させることはできない。もし針灸で、容易に自律神経を操作できるようならば、血圧や体温の恒常性、内臓活動にも支障をきたすので、大変危険な治療ということになりかねない。