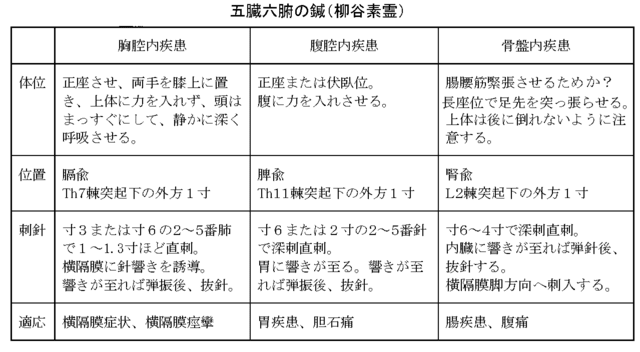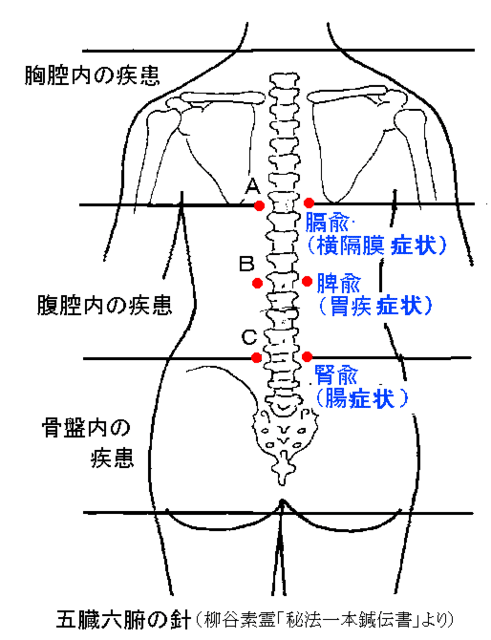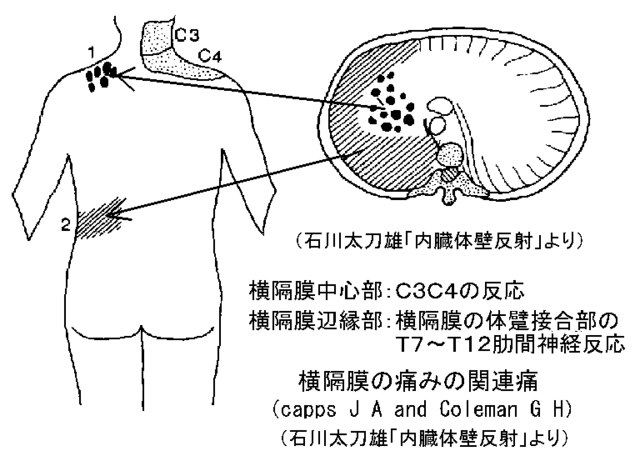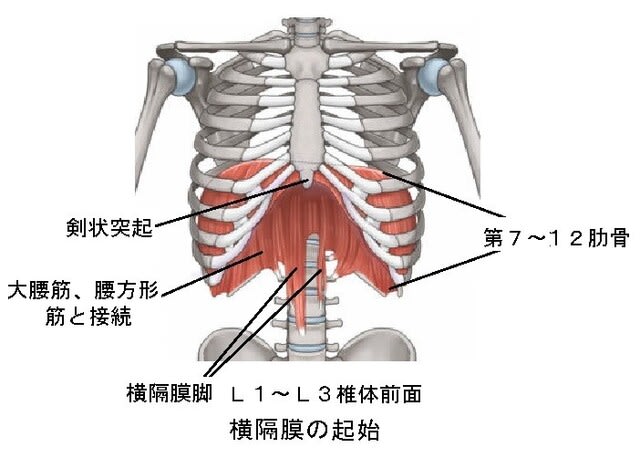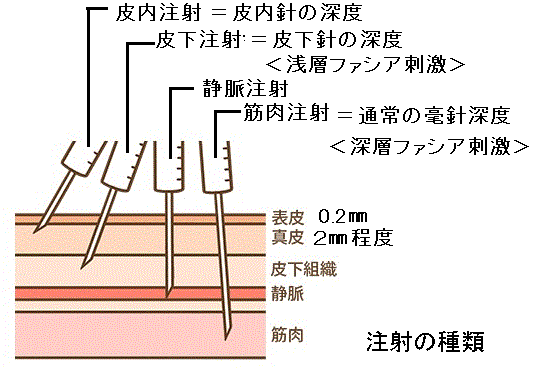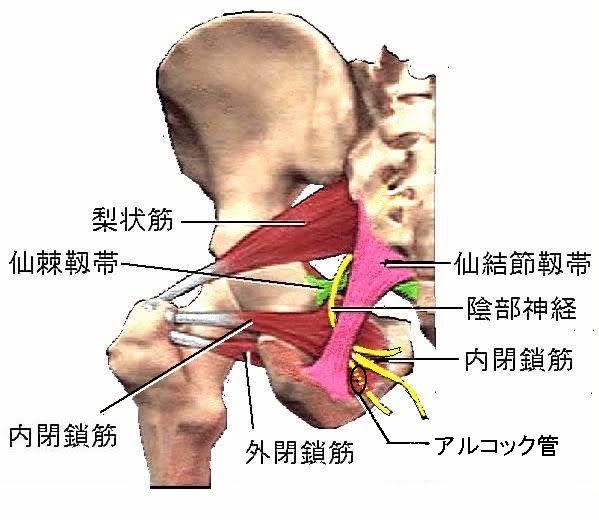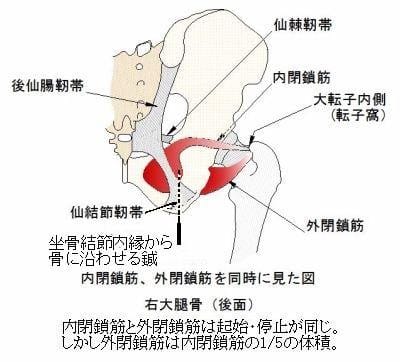前編は、ア~ソまでの経穴名の由来を整理した。ひきつづき、今回は後編としてタ~ワまでの経穴名の由来を整理する。
タ
たいいつ 太乙(胃)
①.太一も同じ意味。北極星のこと。中国の古代思想で、天地・万物の生じる根源。
②「乙」=二番目という意味の他に、つかえて曲がって止まるとの意味がある。道なりに歩いていて途中で急に曲がる。これは大腸の走行を示している。
漢方薬の乙字湯はわが国で考案された便秘の治療薬。
たいえん 太淵(肺) 淵=河川の流れが緩やかで深い場所。ここから渠(人工的な水路)が始めることも多い。 →「経渠」参照
肺経の流れ:沢の水(尺沢)から流れ出て、途中一部は支流(列缺)になって分岐する。本流は人工の水路(経渠)に入り、最後は流れがゆるやかになって大きく深い淵(太淵)に至る。
だいおう 大横(脾) 神闕から大きく離れた部位。
だいかく 大赫(腎) 赫=輝く、火が燃える。本穴の内部には子宮があって妊娠すると、この部が突出して見やすくなる。
たいけい 太渓(腎) 内踝の大きなくぼみ。湧泉から流れ出た腎気の流れがここで一つに集まり、大きな渓流となり、海へ注ぐ。
だいげい 大迎(胃) 大迎骨(下顎骨)と承泣穴と頭維穴からのびる2本の経脈が、このツボのところで迎合している。
だいこ 大巨(胃) 腹部で最も高く、大きく隆起した腹直筋部分
![]()
だいじょ 大杼(膀) 織機の、横糸の間に縦糸を通すのに使われる道具を「杼」という。脊椎の両側に伸びる横突起の形が杼に似ている。
第7頸椎は最も大きい椎体なので大杼とした。
![]()
たいしょう 太衝(肝) 「太」は大きい、「衝」は要衝のこと。肝経の原穴であるから、旺盛な気血が巡る穴なので太衝と呼ぶ。
だいしょう 大鐘(腎) 踵骨を後からみると鐘のような形をしていることから。
だいちょうゆ 大腸兪(膀) 大腸の診療に用いる。
だいつい 大椎(督) 第7頸椎(隆椎)が隆起して大きいとの意味
だいと 大都(脾) 「大」は広い。「都」は集まるところ。諸病は広く大きいとこに集まる意味。
だいとん 大敦(肝) 「敦」は大きい、分厚いこと。拇趾の形を敦に例えた。
たいはく 太白(脾)
①古代中国の金星、とくに宵の明星。太陽、月に続く3番目に明るい星として認識されていた。その光が白銀を思わせるところから太白と呼んだ。
②中国には太白山と名のついた山が多数あるが、西安(長安)の西の宝鶏市にも太白山がある。この太白山は西安から見て宵の明星(金星)で、
すなわち太白星がその山上に輝く位置、そして沈む位置にあることから命名。
③太白金星のこと。中国伝統神話に登場する白髪の老人で金星の神様。中国の民族宗教と道教の神。天界と地上との伝令役で、孫悟空を天界に案内した。
![]()
たいほう 大包(脾) 包はまとめるの意味。本穴が脾の大絡で、諸経をまとめることを意味。
たいみゃく 帯脈(胆) 腰に巻く帯の場所。
たいよう 太陽(奇) 最も日差しが強く当たる部位。頭部には髪があるで日差しから守られているので、とくにコメカミを太陽と名づけた。
だいりょう 大陵(包) 月状骨の隆起を、大きな丘陵にたとえた。
だたん 兌端(督) 本穴は上唇の上端正中にある。「兌」は変わるの意味で、外皮と粘膜の間の意味。その境界部であるため兌端と名づけた。
だんちゅう 膻中(任) 古来、両乳間の間を膻という。「膻」にはヒツジのような生臭い においのこと。別名、上気海、上丹田
婦人が、寝ている時など母乳が漏れ出て、膻中あたりにたまり、ヒツジのようなにおいがする。
たんゆ 胆兪(膀) 胆の診療に用いる穴
チ
ちき 地機(脾)
①本穴には女性の月経不順や精血不足、生殖能力の低下などの症状を改善する。その働きが大地に万物の生命が復活するようなので。
②原始的な織機を地機(じばた)とよぶ。地面に杭を立て、そこに糸を引っかけて編んだ。やがて高機(たかはた)に進化した。
杭は、ヒラメ筋起始部が脛骨に付着している「地機穴」になる。
![]()
ちくひん 築賓(腎) 迎賓館をつくり来賓を待つという意味。「賓」とは主人と並ぶ大切な来客。来客に当たるのが、腓腹筋・ヒラメ筋(もしくはアキレス腱)。その境目に属す。
ちそう 地倉(胃) 倉=穀物の貯蔵庫。人は「地」から五味を得て、口から食べて胃の中におさめる。
ちっぺん 秩辺(膀) 「秩」は順序。「辺」は側とか遠いという意味。本穴は背部穴は秩序正しく並んでいる第二行線の最下部に位置するため。
ちゅうきょく 中極(任) 恥骨の上縁の湾曲したところにあるから
ちゅうかん 中脘(任) ①脘=平たく伸ばした干し肉。すなわち腹直筋の中央の穴。
②胃の中央、小湾部
ちゅうしょ 中渚(三) 三焦経で液門穴の次に中渚がある。「液」は少量の水、「渚」は波打ち際。
波に濡れる時と乾いた時がある境界部分であり、液門に比べると乾いている。
ちゅうしょう 中衝(包) 中指動脈の拍動部。「中」=中指、「衝」=要衝、重要な場所。心包経の気血は、中衝から、流れ込むから。
ちゅうすう 中枢(胃) 「天」は上部を指し、「枢」は枢軸・要の意味。臍の傍にあり、臍を境に天と地(上半身・下半身)の境目の要所。
ちゅうちゅう 中注(腎) この内側には胞宮や精巣があり、腎気が集まるところで、ここから胞中(子宮)へ注がれるから。
ちゅうてい 中庭(任) 「庭」=宮殿(君主)の庭園。膻中(宮殿)の下に位置する。胸郭は庭園で膻中は宮殿真下にある中庭。
ちゅうと 中都(肝) 『中』は中央、『都』は集合する意味。気血がここに集まる。
ちゅうとく 中瀆(胆) せまい水道のことを「瀆」という。腸脛靱帯と大腿二頭筋との間にできる溝を狭い排水路である瀆に例えた。
ちゅうふ 中府(肺) 「府」は圧痛なる、肺経の気はここから体表に現れる。
ちゅうふう 中封(肝) 「中」は真ん中、「封」は封鎖される。長母指伸筋と前脛骨筋に挟まれた中央。
ちゅうりょう 肘髎(大) 「髎」は骨の突起の近くにある陥凹、あるいは間隙を指す。肘関節の外側陥凹にある。
ちゅうりょう 中髎(膀) 第3後仙骨孔の穴
ちゅうりょゆ 中膂兪(膀) 「膂」とは背中の左右の筋群。膂骨とは背骨。膂力は背中の筋肉の力で、腕力は腕の筋肉の力。
ちょうえ 聴会(胆) 「会」は集まる。本穴は耳聾や気閉を治し、音が集まり、聴覚が戻るという意味。
ちょうきゅう 聴宮(小) 聴力にとって要となる場所
ちょうきょう 長強(督) 脊柱は長く強い骨。督脈は全身の陽気が集まりその気は強く盛んであるため
ちょうきん 輒筋(胆) 「輒」(ちょう)は荷車の側板のこと。並んだ板が肋骨に似ている。「輒」んみは耳朶のように軟らかいとする意味がある。
これは側胸部の前鋸筋の筋腹が、耳朶のように軟らかく丸い形に見えることから連想されている。
![]()
![]()
ツ
つうこく 足通谷(膀) 通りすぎることを「通」、陥凹を「谷」という。足の経気が通りすぎるところのため名づけられた。経気が腎経の然谷に向かうところ。
腹通谷(腎) 黄帝内経に『谷の道は脾を通ず』とある。水穀(飲食物)を上から下へ流す穴という意味。
つうてん 通天(膀) 頭頂部の意味。
つうり 通里(心) 絡穴。心経の気血の流れはここで裏まで通り、太陽経小腸 経に絡む。
テ
てんけい 天渓(脾) この場合の「渓」は乳汁分泌を川に例えている。
てんしょう 天衝(胆) 「天」は頭頂にある百会穴のこと。「衝」は通ずる道のこと。 本穴は百会へ通ずる道の役割を持つ。
てんすう 天枢(胃)
①北斗七星の第一星 →「璇璣」参照
②上半身と下半身は、この軸枢を境にして分ける。「枢」は蝶番が発明される以前は、回転扉の回転軸のことだった。
![]()
てんせい 天井(三) 「天」=上半身。「井」=陥凹。本穴は肘の後ろで肘を屈曲したときにできる陥凹部にあり、経気が深部に集まるところ。
てんせん 天泉(包) 肋間に溜まった池の水(天池)が、上腕二頭筋筋溝(天泉)に流入する部。
てんそう 天宗(小) 「天」は上部、「宗」は中心。肩甲骨の中心にあることから名づけられた。
てんそう 天窓(小) 「天」は頭を指し、「窓」を穴。頭部にある七つの竅(耳・眼・鼻・口)。七竅の疾患を治すため。窓を開け気の通りをよくする穴。
てんち 天池(包)
①天池との地名は多数あるが、代表的なのは、中国と北朝鮮の国境にある白頭山にある池のこと。
②肋間のくぼみのような池。
てんちゅう 天柱(膀) 天を支える柱。天とは頭蓋骨のこと。頸椎を天柱骨とよぶ。
てんてい 天鼎(大) 鼎とは三つの脚と二つの耳をもった煮炊き用食器。三脚とは左右の胸鎖乳突筋と後頸部筋。耳は取っ手の部分。
てんとつ 天突(任) 胸骨頚切痕の上に向かう形状より
てんぷ 天府(肺)
①天は上部の意味で気が肺の上部に集まること。
②天から与えられた肥沃な土地。成都のこと。
てんゆう 天牖(三) 「天」は人体の上部を指し、ここでは頭項部のことである。
「牖」は窓口で、頭部に竅があるという意味である。このツボが主に頭風、耳竅などの病変を治す。
てんよう 天容(小) 「天」=頭部、「容」=引き入れる・受け入れる。頭頚部の疾患に有効なため。
てんりょう 天髎(三) 肩甲骨上角の隙間。「髎」は隙間このこと。
ト
どうしりょう 瞳子髎(胆)「瞳子」=瞳孔。「髎」は骨の隙間。眼窩との隙間。
とうどう 陶道(督) かまどで陶器をつくる火の通路のこと。解熱の要穴。
とくび 犢鼻(胃) 犢=仔牛。膝蓋靱帯を仔牛の鼻に例えた。ちなみに仔牛の両目は、内膝眼と外膝眼になる。
ナ行
ないかん 内関(包) 腕の内側にある関所。
ないてい 内庭(胃) 「内」=深部、「庭」=居住地。遠く離れた頭部・心部・腹部などの疾患を治す。その作用は表より内や裏にあることから。
にゅうこん 乳根(胃) 乳頭の根元
にゅうちゅう 乳中(胃) 乳頭部
ねんこく 然谷(腎) 然骨とは舟状骨のこと。
のうくう 脳空(胆) 「空」は孔や陥凹。本穴は脳戸の横で、後頭骨下部の陥凹部に挟まれている。
のうこ 脳戸(督) 出入りする処を「戸」と呼ぶ。脳の気が出入りする場所。
ハ
はいゆ 肺兪(膀) 肺の診療に用いる穴
はくこ 魄戸(膀) 肺兪の傍にあり肺は魄を蔵する。死ぬと呼吸をしなくなる(気が動かない)ので、魄も消滅する。
魄の解字は白+鬼で、魂(=気)を失った白骨死体をさす。戸は門(中に入るのを防ぐ)で、この場合の骨とはとくに肋骨を示す。
はっかんゆ 白環兪(膀)「白」は白色、「環」は金や玉の貴重品。女性の帯下や男性の精液は白色なので、人体の性を蔵するところ。
ヒ
ひかん 髀関(胃) 「髀」は大腿骨上部をさす。関は関節の意味。
ひじゅ 臂臑(大) 「臂」は上腕部。「臑」は柔らかい肉で、三角筋と上腕三頭筋の間をさす。
ひゃくえ 百会(督) 多数の経絡が会する場所。
びしょう 眉衝(膀) 眉毛を動かすとこのツボまで、突き上げるような動きがある。
ひゆ 脾兪(膀) 脾の診療に用いる穴
ひよう 飛陽(膀) 膀胱経は、ここで絡脈が分かれ、絡脈は腎経へ行く。
フ
ふうふ 風府(督) 風邪があつまるところ。風邪は頭項部を冒しやすい。
ふうち 風池(胆) 後頸部の陥凹部で風の吹きだまり
ふうもん 風門(膀) 風邪が侵入する門
ふくあい 腹哀(脾) 「哀」は泣き叫ぶこと。腹の音が悲鳴のように聞こえること。
ふっけつ 腹結(脾) 腹気すなわち腸の蠕動を調整する。腹の脹満を治する。
ふくと 伏兎(胃) ウサギが丸まって伏せている形
ふくりゅう 復溜(腎) 水の流れは太谿→大鐘→水泉→照海と、内果下の平らな処を一回りした後、再びここへと上行する。
ふげき 浮郄(膀) 「浮」は上下に漂っている状態。「郄」は孔や陥凹をさす。委陽穴の上の陥凹部にあるため。
ふしゃ 府舎(脾) 「府」は腑と同じ。「舎」は部位。六腑の治療に関係する。
ふとつ 扶突(大) 一扶とは四本指を並べた幅(3寸)のこと。突とは喉頭隆起のこと。喉頭隆起の横にある鎖骨から3寸上にある穴。
ふはく 浮白(胆) 脈気が軽く浮いて上昇することを指す。「白」は昔から「百」に通ずる。脈気が天衝を経て、頭頂の百会に到る。
ふぶん 附分(膀) 「大杼」穴から分かれて支脈となり本経と並走する。
ふよう 不容(胃) 胃の噴門にある。本穴の高さまで食物が達したらそれ以上は受容不可能(受容能力の限界)との意味、
ふよう 跗陽(膀) 「跗」は足背のこと。足背にある陽のツボ。
ヘ・ホ
へいふう 秉風(小) 禾は稲束、秉は稲束を手にもつこと。稲束を背中に背負い、風をさえぎる。風邪をさえぎっている。
へんれき 偏歴(大) 「偏」は斜め、「歴」は通過を意味。大腸経の絡穴で、ここから分かれて肺経に向かって斜めに走ること。
ほうこう 胞肓(膀) 「胞」は子宮、「盲」はあぶらみの膜。子宮内膜 のこと。
ぼうこうゆ 膀胱兪(膀) 膀胱の診療に用いる穴
ほうりゅう 豊隆(胃) 下腿前面の筋が豊かに隆起した部位。
ぼくしん 僕参(膀) 僕=自分をへりくだった名称。昔、しもべの者がご主人に挨拶するとき、膝を屈し指先をこの部までもっていった。
ほろう 歩廊(腎) 建築用語で、二列の柱を繋ぐための通路・回廊のこと。「中庭穴」を跨ぐように歩廊がある。歩廊により腹直筋停止が連結している。
![]()
![]()
![]()
歩廊の一例
ほんじん 本神(胆) 脳は人の根本で、元神の府である。本穴は前頭部で、神庭穴の横にあり、その内部には脳がある.。
神社の建物でいえば、神庭は拝殿、本神は本殿、その先には脳(=御神体)へ通ずる頭維がある。
![]()
メ・モ・ユ
めいもん 命門(督) 臍帯は胎児に栄養と酸素を送る、いわば生命のよりどころ。その裏側になるので、命の門と名づけた。
もくそう 目窓(胆) 「目」は眼、「窓」は光を入れる窓のこと。眼疾患を治し、眼の窓(瞳孔)を散大させる。
ゆうせん 湧泉(腎) 足底にあり。足の腎経の気血が沸いてくる部。
ゆうもん 幽門(腎) 「幽」はかくされたものを指し、「門」は門戸を指す。胃の上部を指している。腹から胸に経気が流れるため。
解剖学の胃の下門とは無関係。
ゆふ 兪府(腎) 「兪」は輸送する。「府」は集まるところ。腎気が足から胸へ運ばれ、最後にここに集結するから。
ヨ
ようかん 腰陽関(督) 足陽関と区別する必要から腰陽関とした。陽気の関所。
足陽関(胆) 「陽」は膝外側(陽側)、「関」は関節を指す。
ようけい 陽渓(大) 「陽」は陽経の意。「谿」は山に挟まれた溝、肉の小会するところ。
手首を曲げるときに現れる陥凹部が山間の谷に似て いるため。また、この経穴は大腸経の経火穴である。
ようこう 陽交(胆) 胆経と陽維脈の交会穴であることから。
ようこう 陽綱(膀) 「綱」は統括すること。本穴は膀胱経に属し、胆兪の横にあり、胃兪・三焦兪・大腸兪・小腸兪・膀胱兪の上にある。
六腑は陽であり、本穴はその最上位にあって、他の陽を統括している。
ようこく 陽谷(小) 「陽」は陰陽の陽の意味で、「谷」は陥凹。尺骨頭と三角骨の間の陥凹部にあり、形が谷のようであることから名づけられた。
ようそう 膺窓(胃) 「膺」は胸、「窓」は気と光を通すところの意味であり、胸部の閉塞を通すため。
ようち 陽池(三) 手関節背面を背屈してできる中央の陥凹を池にたとえた。
ようはく 陽白(胆) 前額部にある。日の当たる小さな孔。白=小孔
ようほ 陽輔(胆) 古代、腓骨を外輔骨と呼んだことから。
ようゆ 腰兪(督) 「兪」は輸送の意味。腰の脈気がここから転輸されるため。
ようりょうせん 陽陵泉(胆)「陽」は外側、「陵」は腓骨頭、「泉」はその下方の陥凹
ようろう 養老(小) 「養」は有益の意味で、老化に対して有効であることから。
ラ行
らっきゃく 絡却(膀) 絡とは脳に絡む。却は再び体表の本経に戻るの意味
りょうきゅう 梁丘(胃) 土地の高いところを丘、丘の上の背部分を梁と称した。
りょうもん 梁門(胃) 「梁」=柱のハリ。上腹部に現れる横梁のような硬いもの。腹直筋の腱画部にあるため。
りんきゅう 頭臨泣(胆) 「泣」=声を上げずに泣くこと。人は泣く寸前に鼻腔から前頭部にかけて涙があふれてくる。この上腋(=涙)の道を鼻水と涙が下るところ。
「臨」は下に対して上に含まれるという意味。
りんきゅう 頭臨泣(胆) 痛みが甚しい時、涙が反射的 に出る処。
れいきょ 霊墟(腎) ①「墟」は土で盛られた高い山。 霊墟は前胸部の高いところにあり、心神と関係している。
②秦始皇帝が築いた運河。現在の中国の桂林市興安県に現存。
れいこう 蠡溝(肝) 蠡=虫が食べた孔。脛骨の凹みをそのように例えた。
れいだ 厲兌(胃) 「厲」は疫病、疾病のことだが、ここでは胃の激しい症状をいう。「兌」は門戸だが、ここでは口をさす。
口がゆがむなどの症状を治すのに使われる。
れいだい 霊台(督) 「霊」は心霊、「台」は高く平らな地域。物見台のこと。
この穴位の前面は心臓であり、心臓疾患を治療する。
れいどう 霊道(心) 心は神を蔵し神が変化して、霊となる。「霊」は精神、「道」は通路。
れっけつ 列缺(肺) 肺経の列から分かれて欠けるの意味。
れんせん 廉泉(任) 廉はすだれ。舌骨につく筋肉をすだれに例えた。舌下腺の
ろうきゅう 労宮(包)
①「宮」は手掌中央。道具を握ると中指先がここに当たる。
②手を酷使する労働で出現する反応点
ろうこく 漏谷(脾) 「漏」はにじみ出る、「谷」はくぼみ」。脛骨の後ろのくぼみにあり、利尿作用があることを示す。
ろそく 顱息(三) 「顱」は頭、「息」は休息。頭を休めるツボ
ワ
わりょう 和髎(三) 聴力を調和させる骨の陥凹。
わんこつ 腕骨(小) 「腕骨」とは尺骨茎状突起の旧名称。
引用文献
①森和監修:王暁明ほか著「経穴マップ」医歯薬
②周春才著:土屋憲明訳「まんが経穴入門」医道の日本社
③ネット:翁鍼灸治療院 HP
④ネット:経穴デジタル辞典 ALL FOR ONE
⑤漢和辞典「漢字源」学研