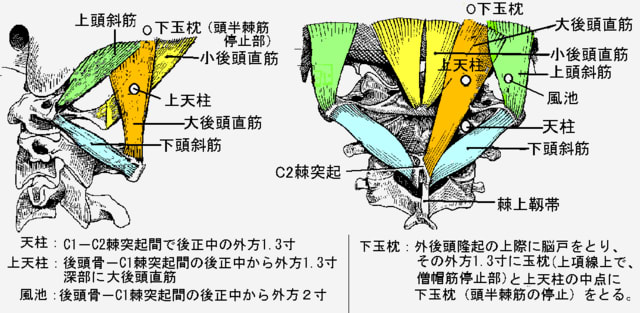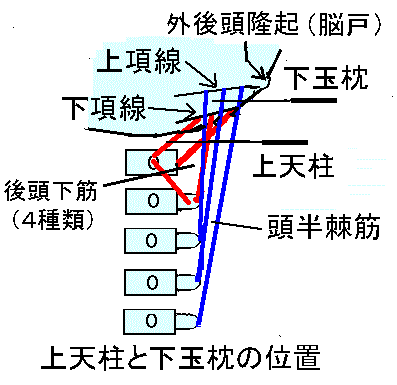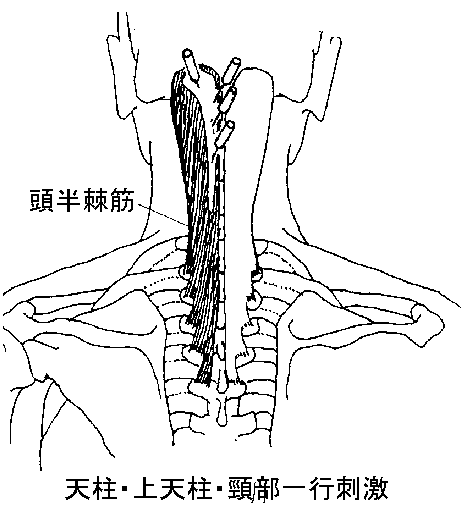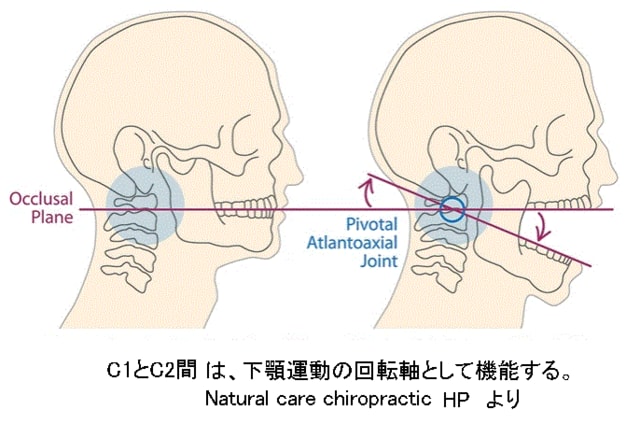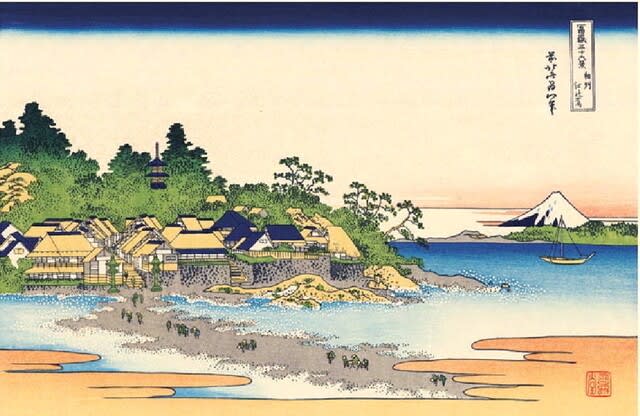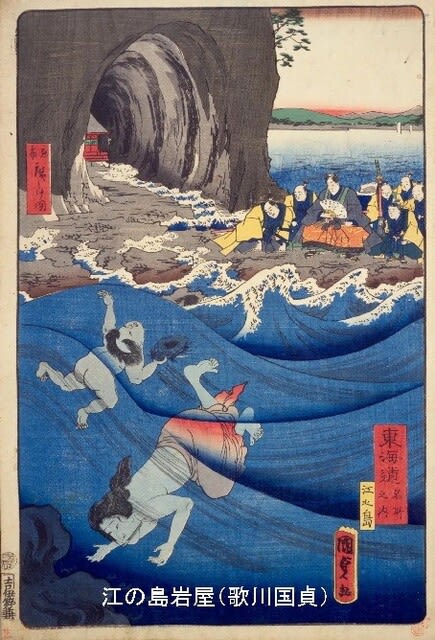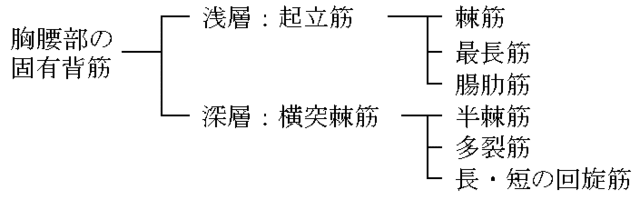肩関節の結帯動作制限に対する針灸治療のブログは、2021.6.15に発表済だが、内容が古くなったので書き改めることにした。
1.結帯動作制限と障害筋
エプロンやブラジャーをする動作または排便後にお尻を拭くという動作を結帯動作という。これは上腕骨の伸展+内旋+外転の複合動作で、これに肩甲骨の下方回旋を伴う。結帯制限は、凍結肩など関節の障害でも起こりうるが、本稿では筋の問題として考えることにした。したがって診断名は肩腱板炎となる。この運動で、とくに内旋制限は結帯動作制限に直結するが、伸展と外転の動作は、前腕を背中側にもっていく過程の動作であり、伸展と外転の動作は、前腕を背中側にもっていく過程の動作であり、必ずしも可動域制限があるわけではない。
結帯動作の語呂:マワシ(結帯)が伸(伸展)びて、不甲斐(外転)ない(内旋)
お相撲さんのマワシがのびて、格好悪いさま。

2.棘下筋
1)棘下筋の過収縮
結帯動作(肩関節の伸展+外転+内旋)制限では、内旋筋である大円筋と肩甲下筋の筋力が弱くて生じているのではなく、拮抗筋である外旋筋(=棘下筋と小円筋)が過収縮状態にあって、これが伸張を強いられて痛みと可動域制限を生じている状態である。

2)天宗運動針
肩の内旋動作では、棘下筋が伸張を強いられる。したがって過緊張状態にある棘下筋を刺激して伸張させることを治療目標とする。次の2方法がある。
①座位で天宗刺針したまま上腕骨を内旋運動させる。
②患側上のシムズ肢位で、患側手掌をベッドにぴたりとつけ、肘を90°屈曲位で天宗圧痛点に刺入したまま、肘の円運動させるとよい。棘下筋に響きを与
えることができる。激量を患者自身で決めることができるメリットがある。我慢できる痛みの範囲内で10回~30回、回すよう指示する。
最新の知見では、結帯動作で母指が体幹を越える処までは、棘下筋下部線維が収縮し、母指が背中を上行する処からは棘下筋上部線維(=肩甲棘の直下)が収縮するとされる。これは天宗の圧痛位置も変化するという。症状の重い結帯動作障害では肩甲骨の下方を刺激し、症状が軽ければ肩甲骨棘窩窩の上方を刺激することがよいのだろう。教科書的に天宗を取穴するのではなく、反応点を探して刺激することが重要だろう。

天宗(小):肩甲棘中央と肩甲骨下角を結んで三等分し、上から 1/3の処。棘下筋中。肩甲上神経(純運動性)刺激。
3)棘下筋のTPの放散痛
棘下筋のTPが活性化すると上腕外側に痛みが出ることがある。逆に上腕外側痛を訴えるケースでは、天宗刺針で症状の再現痛が生じ、治療効果も良好である場合が多い。天宗から刺入して上腕外側に響かせるには、肩甲骨骨膜に十回ほどノックするような刺針刺激を行うとよい。患者は症状のある上腕外部を触ることはできるが、棘下筋を触れないので、患者自身は肩の前方が痛むと訴えることになる。
※近年の知見では、結帯動作で母指が体幹を越えるまでは、棘下筋下部線維が収縮し、母指が背中を上行する処からは棘下筋上部線維(=肩甲棘の直下)が収縮するという。これは天宗の圧痛位置も変化することに他ならない。症状の重い結帯動作障害では肩甲骨の下方を刺激し、症状が軽ければ肩甲骨棘窩窩の上方を刺激することがよいだろう。
かつて中国では、上腕外側痛に対して肩髃から曲池に向けて水平刺を行っていた。これはおそらく上腕皮神経痛を治療しているのだろうが、治療効果は持続しないことが多かった。

4.小円筋
起始→肩甲骨の後面外側縁上部の1/2 停止→上腕骨大結節陵 神経→腋窩神経運動支配
腋窩神経の筋支配語呂:賞(小)賛(三)の駅(腋窩)か。小円筋、三角筋は腋窩神経支配
1)小円筋の過収縮
結帯動作は、伸展+内旋+外転の複合動作である。このうち内旋に働くのは大円筋だが、大円筋の筋力低下による内旋制限は臨床上きわめてマレで、内旋障害は小円筋の過収縮によることがほとんどである。治療は小円筋の緊張を緩めることが目標になる。小円筋が過収縮すると、外旋制限が生じる。これを無理に伸張しようとすると結帯制限が生ずる。
2)臑兪運動針
結帯動作肢位にして、臑兪から小円筋に刺入。肘を体幹前方に動かし、小円筋をストレッチする。臑兪への刺針は単に坐位や伏臥位で刺入するとスカスカするのみで筋に当たったとの手応えがない。
座位で両手を腰にあてる。その際、母指は背中に向ける。肘を手前に動かす。この動きは肩関節内旋動作になる。この時小円筋は伸張されている。この肢位で臑兪から小円筋に刺入。肘を体幹前方に動かし、小円筋をストレッチする。


臑兪(小): 腋窩横紋後端の上方、肩甲棘外端の下際陥凹部で小円筋中。臑兪は側臥位にて肩甲骨外縁を刺入点とし、骨にぶつけるよう刺入する。
腋窩神経の筋支配語呂:賞(小)賛(三)の駅(腋窩)か。小円筋、三角筋は腋窩神経支配
※肩貞と臑兪の位置についての私見
学校協会教科書では、肩貞は腋窩横紋の後端から上1寸にとり、臑兪は肩甲棘外端の下際陥凹部にとる。しかし本稿では肩貞を腋窩横紋の下で大円筋上にとり、臑兪を腋窩横紋下で小円筋上にとっている。その方が臑兪は結帯動作の治療穴に、後述する肩貞は結髪髪動作の治療穴として理解しやすいため。