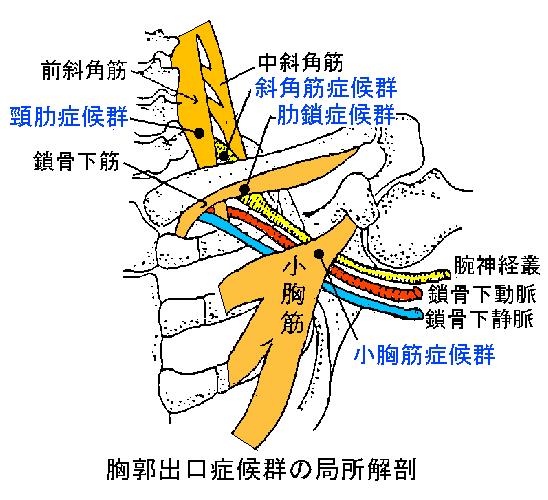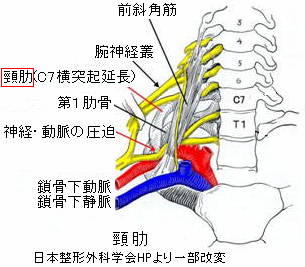これまで色々な意見を発表してきたが、今行っている鍼灸治療で、実際に使っている方法と、すでに使わなくなった方法がある。概ね考えすぎた治療にはろくなものがない。思考は単純なほど実は実効性があると思うようになった。どこまで治療を単純なものにできるかも検討課題である。
1.肩甲上腕関節間隙の痛み
肩甲上腕関節部の特定の一点を痛く感じる場合、そこが治療点となる。具体的には上腕骨頭と峰のつくる第2関節部分が治療点となる。治療点は、肩髃・顴髎・巨骨などから棘上筋腱に対し刺針するようになる。
1)肩腱板炎と腱板部分断裂
①肩髃から棘上筋腱への刺針
肩腱板炎の多くは棘上腱に相当する腱板部位に限局して痛む。棘上筋腱は、大結節に付するので、その経穴部位である圧痛ある肩髃に刺針し、針先を棘上筋腱に入れる。
※棘上筋の腱部は、構造的に血行不良になりやすい部であることから、カリエはcritial zone(危険区域)とよんだ。

②肩髎から肩髃への透刺(柳谷素霊の方法)
柳谷素霊の棘上筋に連続した肩腱板部の痛みに対しては、2寸針を用いて、肩髎から肩髃へ刺針を得意としていた。肩髎から肩髃への透刺は、カリエの述べた危険区域部への刺激として、適切であることがわかる。単に肩髃や肩髎から刺針するのと異なり、刺激目標が明確になるので刺針に手応えを感じる。実際に治療効果も優れている。
③巨骨から棘上筋部への刺針(似田)
体位:側臥位でタオルで薄いマクラを使用。頸を側屈位にさせる。
治療点:巨骨ではなく、肩井を刺入点とした方が針を鎖骨肩峰アーチ下をくぐらせやすい。
刺針:3寸針を用い、肩井を刺入点として巨骨方向に斜刺し、針先を棘上筋腱部付近に達させる。達したか否かは、刺針した状態でゆっくりと狭い範囲で上腕を外転運動させると、針が動くことで確認できる。その後5分ほど置針。


2.上腕外側痛の痛みと天宗刺針
上腕外側は腋窩神経の分枝である上外側上腕皮神経知覚支配で、この神経は腋窩神経の分枝なっている(腋窩神経の本幹は小円筋・三角筋を運動支配し、腋窩神経はさらに肩関節包下方 知覚支配している)。この解剖学的性質から、上腕外側痛に対する局所治療としては肩髃から曲池方向に水平刺するのかよいと考える者がいる。さらに一歩進めて腋窩神経刺激を目的に後四角腔部(=肩貞)から直刺しても有効だと考える者もいると思う。しかし実際には、このような刺針は直後数時間の鎮痛効果しかもたらさないことを痛感する。
 痛感
痛感

ここで棘下筋のトリガーポイントの図をみると、棘下筋仲のトリガー(天宗あたり)が活性すると三角筋部や上腕外側部に疼痛症状をもたらすようだ。ではどういった状況で棘下筋のト ガーが活性化するのだろうか?

肩甲上神経は肩関節を外転・外旋する筋肉である棘上筋・棘下筋を運動支配している。肩甲骨位置異常や繰り返しの動作により、肩甲上神経が引っ張られ神経が過敏になったり、棘上筋・ 下筋を過度に使用(腕を上方・横に捻る)したり、転んで肩後部を打ち付けることなどにより、痛みが出るということらしい。
なお結帯動作制限は非凍結期の五十肩でしばしばみられるものだが、棘下筋・小円筋が伸張された結果なので、天宗・肩貞の圧痛点への運動針が有効になることが多い。
※肩甲上神経
運動支配:棘上筋・棘下筋
知覚支配:なし。ただし肩関節包上部と後部を知覚支配
※腋窩神経
運動支配:小円筋・三角筋
知覚支配:上外側上腕皮神経として上腕外側を知覚支配。肩関節包下部を知覚支配
3.後方四角腔部(≒肩貞)の痛みと肩甲下筋
腋窩神経は肩関節下方の関節包知覚を配しているので、凍結肩時この辺の関節癒着があれば、やはり後方四角腔部の痛を訴える。なお後方四角腔とは、後腕つねにある4筋と肩甲骨外縁のつくる陥凹ある。4筋とは上腕三頭筋外側頭・同の長頭。大円筋・小円筋である。
筆者は後方四角口腔の痛みを改善する目的で、後方四角腔にある腋窩神経ブロック点からから何度も直刺深刺してみたのだが、一向に有効な治療とはならなかった。そこで次のように刺針方向を変えてから、効な針ができるようになった。

1)肩貞からの大円筋・肩甲下筋水平刺
患側上の側臥位。後方四角腔(≒肩貞)を刺入点とし、中国針で肩甲骨と肋骨の間隙に刺すると、針はまず大円筋を貫き、次いで肩甲下筋に刺入できる。トラベルにより、肩甲下筋の TPsは後方四角腔部に痛みを生ずることが調べられている。


2)膏肓からの肩甲骨・肋骨間に入れる水平刺
肩甲下筋に刺針するには、肩貞水平刺のように肩甲骨外縁を刺針点として選択するほか、肩甲骨内縁(膏肓あたり)を刺針点とし、そこから肋骨と肩甲骨間に針を入れていく方法もある。筆者はともに行うが、膏肓から刺針する方がやりやすさを感じる。
治療側を上にした側臥位をとらせる。膏肓あたりから肩甲骨と肋骨間に向けて、5~7㎝平刺すると、ズンという針響を肩甲骨裏面に与えることができる。人によっては、やっとつい処に当たったと喜ぶ者もいる。強く響かせるには、刺針した状態で肩関節の自動外転動作行わせると良く、これは肩甲骨-肋骨間の癒着を剥がす目的で行うには有利である。
肩甲骨の動きが悪い凍結肩では、肩甲骨内縁から肩甲骨-肋骨間の間隙に刺針し、癒着に針先を命中させ、コツコツと骨膜刺激を繰り返すことで、徐々に癒着を剥がしてゆく。


4.三角筋前部や三角筋粗面部の痛み
外転運動の主動作筋である三角筋中部線維と棘上筋の緊張。美容師・理容師など長時間の上外転姿勢保持しなくてはならない者に多い。老化現象とは関係が薄い。
1)症状:上腕挙上時の、三角筋前部線維や三角筋粗面部(臂臑穴あたり)の痛み。痛みを我すればROM正常。
※臂臑(大腸):肩髃から曲池に向かって下がること3寸。三角筋前縁。
2)病態:三角筋前部線維は上腕前方挙上時の主動作筋であり、上腕の前方挙上時には筋の伸時痛が好発する。
3)針灸治療
①三角筋停止部(臂臑)水平刺運動針
三角筋は上腕骨外側で上腕骨頭側から1/3の部にある臂臑穴(三角筋粗面部)に停止するが、この部の痛みを訴える者がいる。2寸の中国針を用い、矢状面で前から後に向け、三 筋粗面に刺入する。 (北京堂、沼袋治療院HPより)
②三角筋起始部水平刺運動針
肩関節が痛むと訴える患者で、三角筋始部の圧痛は高率にみるが、患者自身は痛部位を認識していないことが多い。三筋の筋起始部症と捉え、鎖骨の下で三角起始部を鎖骨と水平に刺針、その状態で腕の上げ下げを5回程度、痛みが強く出い程度に行わせる。自動運動時、施術者上腕を介助する。
③術者の肩に手を乗せて三角筋起始部運動針肩関節を外転させて圧痛を調べる方法がある。座位で施術者も椅子に向かい合って座り、患者は患肢で施術者の肩甲上腕部を軽くつかむ(前方挙上90度姿勢を保持)。この状態で三角筋部圧痛点(とくに肩甲骨起始部)に刺針し、運動針する。
5.上腕二頭筋長頭腱々炎部に対する肩前穴斜刺
独立した病態としての上腕二頭筋長頭腱々炎では、結節間溝部(=肩前穴)を取穴。肩穴から曲池方向に斜刺し、針先を上腕二頭筋長頭腱に刺入。軽い雀啄を行って抜針するという治療が考案できる。ただし結節間溝部は、鎖骨肩峰端の直下にあり、また三角筋に覆われていているので圧痛の無を調べることは必ずしも簡単ではない。
上腕二頭筋長頭腱々炎の炎症は、単独で現れるより、肩峰下滑液包の炎症が上腕二頭筋長頭腱部に拡大した場の方が多く、肩髃刺針を併用することが多い。